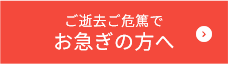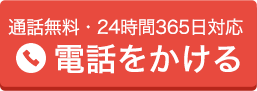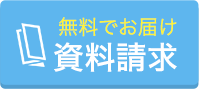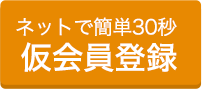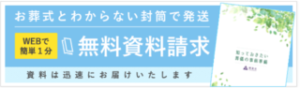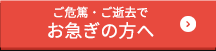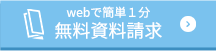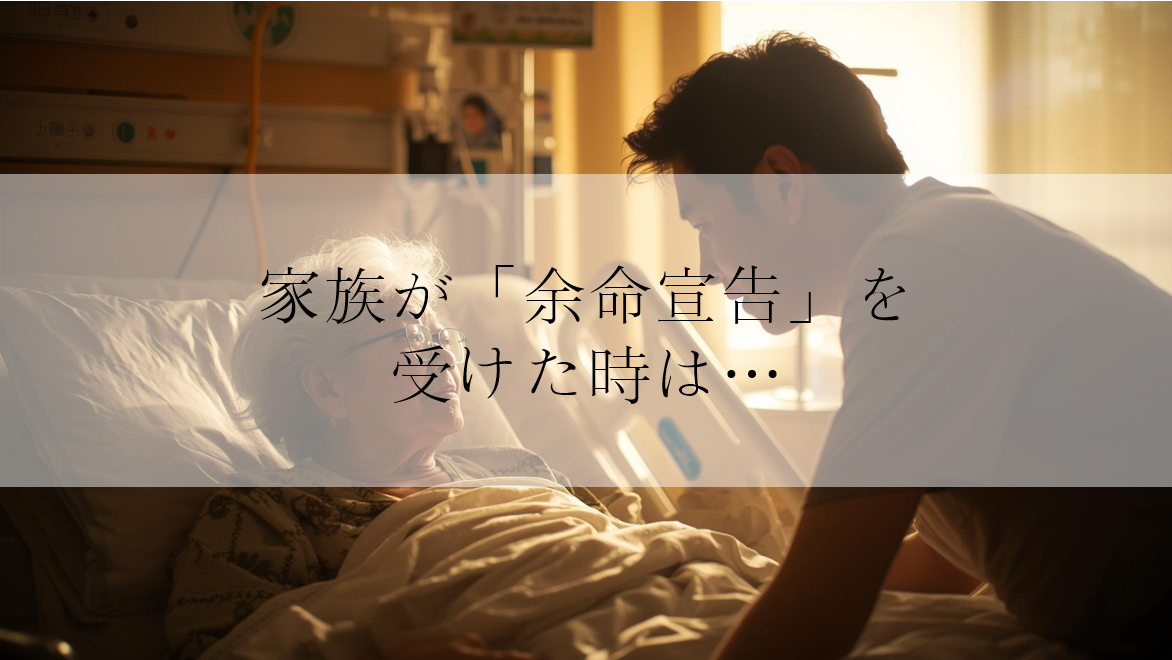
■「余命」は必ずしも残された寿命ではありません
医師から大切な方の余命について告げられたら、誰でも大きなショックを受けて当たり前です。ただ、この「余命宣告」は患者さんの病状を基本に、病気生存率や治療期間などの統計データ、個々の症例など医師の経験値から導き出された生存期間に関する「予測」で、必ずしも正確とは言い切れないものです。楽観視はできませんが、希望は残しておきましょう。
<余命宣告は本人に伝える?伝えない?>
最近はあらかじめ知っておきたいと希望する方が多く、医師から本人に直接伝えるケースが増えています。一方、家族だけが余命宣告を受ける場合もあり、本人に伝えるかどうかの難しい判断が家族に委ねられることもあります。本人の性格やその時の状態、深刻度などによって、病気の進行を早めてしまったり絶望させたり、といった可能性もあるため、慎重に判断するしかありません。担当医や支援センターなどとも相談してみましょう。

<家族が余命1か月の際、本人にしてあげられること>
余命宣告を受けたのが家族だったとしても、頑張るのは本人だけではありません。家族がしてあげられることもたくさんあります。例えば、以下のようなことがあげられるでしょう。
■精神的なサポート
気持ちに寄り添う: 相手の気持ちを受け止め、そばにいることを大切にする。
前向きな言葉をかける: 無責任な励ましは避け、そばにいること自体が心の支えになることを意識する。
日常を大切にする: 可能な限り普段通りの会話を心がけ、安心できる日常の雰囲気を作る。
■本人の希望を叶えるサポート
やりたいことを聞く: 家族との思い出作りや、行きたい場所など、
本人の希望を可能な限り叶える手助けをする。
最期をどう迎えたいかを聞く: どんな最期を迎えたいか、臓器提供の意思があるかなどを確認する。
■終活のサポート
病気について正しく理解する: 治療方針などを家族全員で理解し、情報共有する。
エンディングノートの準備: 葬儀や財産に関する希望を書き留める手助けをする。
相続や遺言書の準備: 財産目録の作成や遺言書の準備などを手伝い、後々のトラブルを防ぐ。
■身体的なケア
食事の工夫: 栄養士や看護師と相談しながら、本人が食べやすい食事を提供する。
快適な環境を整える: 快適に過ごせるよう、部屋の環境を整え、優しくマッサージする。
医療スタッフと連携する: 医療スタッフと連携を取りながら、身体のケアを行う。

<ご自身が「余命宣告」を受けた時は>
病気について、治療について、医師や家族としっかり話しておきましょう。特に治療方針に関しては本人の意向が尊重されますので、自分の意志を明確にしておきたいものです。もちろん病状や経過、家族の生活の都合などで100%実現するわけではありませんが、望まないことを我慢する必要はありません。少しでも元気がでてきたら、できることからチャレンジしてみましょう。「余命が限られている」ことを武器にして、少しわがままを言っても周囲は許してくれると思います。
<残された時間の療養について>
統計では、「家族に迷惑をかけたくない」という思いが強く診られます。でも、家族が「こうしてあげたい」と考えていることは、迷惑でもなんでもありません。日常の細やかなことでもコミュニケーションを図り、お互いに無理や遠慮をすることなく過ごしましょう。
<保険や財産の話>
大切な人は亡くなった後も、残された家族には日常生活が続きます。葬儀に関わる費用や遺品の整理、財産分与などで混乱する可能性も出てきます。もし本人に希望があるのなら、家族との話し合いを行い「遺言書」や「エンディングノート」などで残すことも考えましょう。
<自分の葬儀への希望>
人生最後のセレモニーとなるお葬式。自分が「こうしてほしい」と思うことがあったら、伝えておきましょう。来て欲しい人、呼んで欲しい人の中には、家族が連絡先を知らない場合も考えられるので、リストを作成しておくのも有効です。お別れの時の遺影写真を事前に撮影することも準備のひとつ。元気なうちに自慢の「この1枚」を残しておきましょう。